画像生成AIで副業しようとした僕が、
最初にぶつかった“著作権の壁”
「夢の入り口にあった壁」
「画像生成AIで副業ができる」
そんな記事や動画を見て、僕はすぐに飛びついた。
AIでイラストを作って販売、アイコンやデザイン案件で収益化
——一見すると夢のような話だ。
実際にやってみると、確かにAIは一瞬で画像を作ってくれる。
クオリティも素人が描いたものよりずっと上。
「これならいける!」と思った。
ところが数日後、僕の前に立ちはだかったのは“著作権”という大きな壁だった。
「案件に応募できなかった夜」
僕が最初にやろうとしたのは、AIで生成したキャラクターアイコンを販売すること。
Twitterやココナラには「アイコン用イラスト承ります」という案件が山ほどある。
そこに「AI生成×低価格」で勝負できると思った。
しかし、調べれば調べるほど不安が募った。
- AIが学習したデータは著作権的に大丈夫なのか?
- 有名キャラに似てしまったらアウトでは?
- 商用利用のルールがツールによって違う?
特にStable DiffusionやMidjourneyなど海外発のサービスは利用規約が英語で、
読めば読むほど曖昧だった。
「これって売っていいの? それとも完全にNG?」
はっきり分からないまま、案件に応募する勇気が出なくなった。
机の上には、生成したアイコン画像のフォルダだけが並んでいた。
応募できなかった虚しさと、自分の無知への苛立ちが同時に押し寄せてきた夜だった。
「世界的に続くグレーゾーン」
画像生成AIの著作権問題は、世界的にもまだグレーゾーンが多い。
- 学習データの著作権
AIが学習した画像が既存の作品なら、生成物も「二次的利用」と見なされる可能性がある。
文化庁も「AIと著作権に関する整理」を発表しており、まだ明確な答えは出ていない。
出典:文化庁「AIと著作権」 - 類似性リスク
有名キャラクターや既存作品に似すぎると、著作権侵害や商標権侵害となる恐れがある。 - 利用規約の差
Stable Diffusion:オープンソース、商用利用可能
Midjourney:有料プランのみ商用OK
その他サービス:利用規約によって商用可否が異なる
経済産業省もAI活用に関する契約ガイドラインを公表しており、
リスク管理は利用者側に委ねられている。
出典:経産省「AI・データ契約ガイドライン」
実際、2023年には海外で
「AI生成イラストを販売して著作権侵害を指摘されたケース」が報告されている。
つまり、法的に“完全に安全”と言えるラインはまだ存在しないのだ。
再現チェックリスト|案件に応募する前に確認すべき3点
✅ ツールの利用規約で「商用利用可」と明記されているか?
✅ 生成物が有名キャラや既存作品に似すぎていないか?
✅ 「AI生成」であることを明示する方針を決めたか?
この3点をチェックするだけで、大きなトラブルを避けられる。
「AIはツール、責任は人間」
僕が学んだのは、AI副業は「著作権を理解している人」だけが武器にできるということだ。
- 商用利用OKのツールを選び、利用規約を必ず確認する
- 有名キャラや既存作品を連想させる生成は避ける
- 「AIで作った」ことを隠さず明記する
また、AI生成そのものではなく、
自分の経験や編集を組み合わせることが差別化にもリスク回避にもなる。
たとえば「AIでベースを作り、自分で加工・仕上げする」ことで、オリジナル性を高められる。
AIは強力なツールだが、使い方を誤れば“リスク爆弾”にもなり得る。
知らないまま飛びつくのではなく、理解して責任を持つこと。
これが副業としてAIを使うための最低条件だと痛感した。
「ルールを知ることもスキルの一部」
画像生成AIは確かに夢がある。
でも、その夢の入り口には必ず「著作権の壁」が立ちはだかる。
僕はそこで足を止めたけれど、この経験で
「稼ぐには技術だけでなく、ルールを理解する力も必要だ」と学んだ。
もしあの日、無知のまま販売していたら、
今ごろトラブルに巻き込まれていたかもしれない。
副業は挑戦することが大事。
でも、「知らなかった」では済まないリスクもある。
——AIは画像を生む。
でも責任を負うのは、いつだって人間だ。
FAQ|よくある質問
Q1. AIで作ったイラストをココナラで販売してもいい?
→ ココナラ利用規約では「自ら創作したオリジナル作品」のみ販売可とされており、AI生成物は
注意が必要。必ず最新規約を確認。
Q2. 海外ツールのAI画像を日本で販売しても大丈夫?
→ 基本的には利用規約に従う。ただし日本の著作権法も適用されるため、類似性が高い作品は
リスクあり。
Q3. トラブルを避ける一番の方法は?
→ 「AI生成」と明示すること、自分の編集を加えること、著作権的にグレーな案件には
応募しないこと。
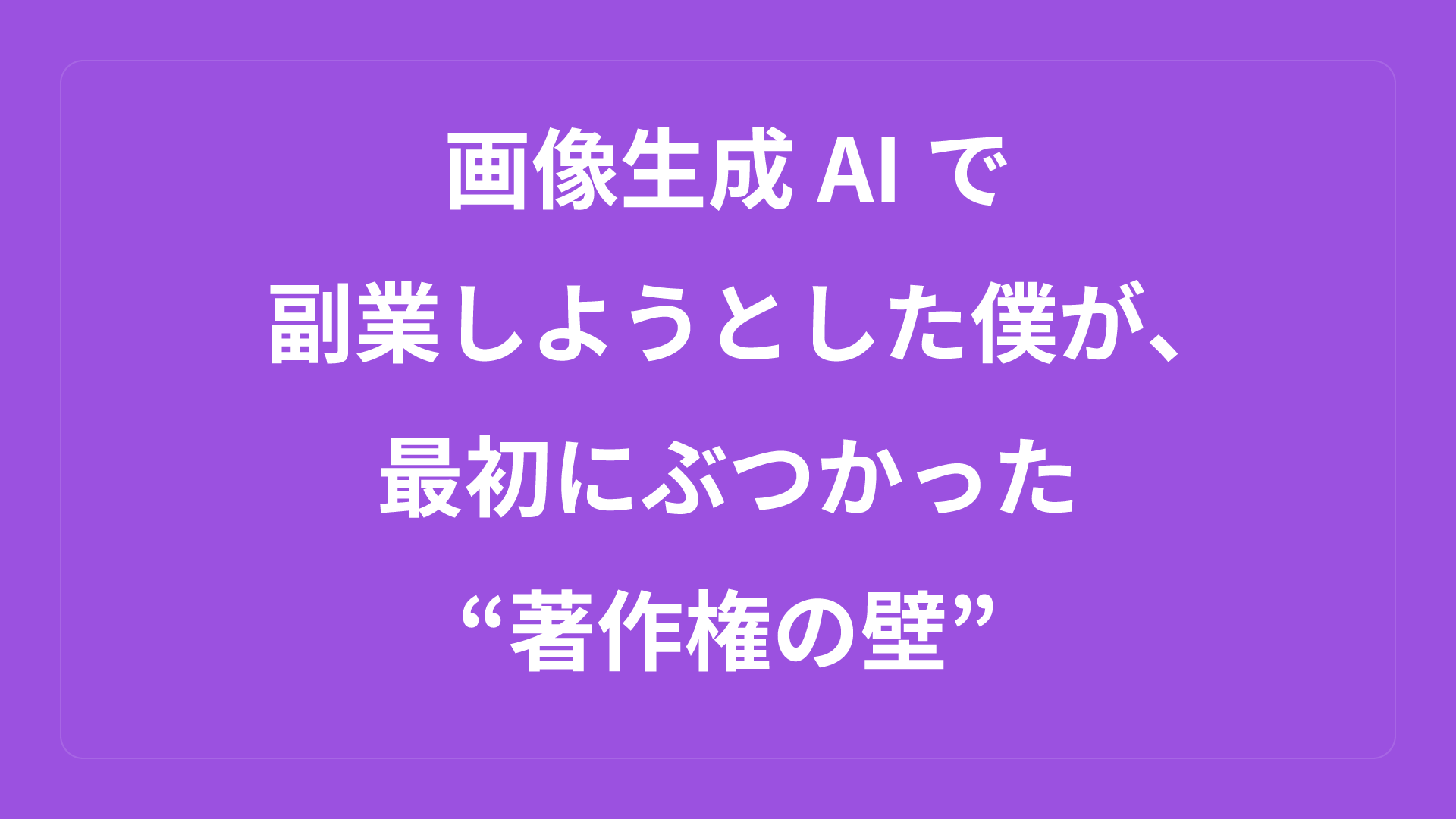
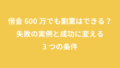
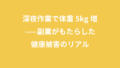
コメント