ChatGPT全盛でも副業ブログが伸びなかった理由——AIに勝てるのは感情か?
「AIと個性、避けられない問い」
ChatGPTをはじめ、AIが副業の世界にも一気に浸透した。
「ブログ記事はAIで量産できる」「SNS運用もAIが最適化する」
そんな声を聞くたびに、ふと疑問が浮かぶ。
——“自分の個性”って、AIに勝てるんか?
僕が持っているのは、特別なスキルでもなく、圧倒的な実績でもない。
あるのは泥臭い失敗談と、少しひねくれた文章くらいだ。
そんなものが、AIの整った文章相手に通用するのか。
副業者として、試さざるを得なかった。
「効率爆上がり、しかし反応は無風」
僕の副業は、ブログ運営とクラウドソーシングでのライティングが中心だった。
AI導入前は、1記事に半日かけるのが当たり前。構成を練って、調べて、文章を削って……
ようやく形になる。
ところが2023年末、ChatGPTを使い始めたら状況は一変した。
記事構成は30秒
本文は数分で2,000文字
SEO的にも破綻のない形
効率は爆上がりだった。
だが公開後の反応はほぼゼロ。
アクセスは伸びず、SNSに投稿しても「いいね」は1件もつかない。
時間をかけずに量産できるはずが、結果は静まり返ったままだった。
その一方で、自分の手で泥臭く書いた「せどりで30万円失った話」の原稿を
読み返したときだけは、不思議と感覚が違った。
数字にはならなくても、「これは自分の言葉として残せる」と感じたのだ。
公開すらしていないのに、完成した原稿を前にした時の胸の奥の重みが、
AIで量産した記事とは決定的に異なっていた。
「AIの強みと決定的な弱み」
AIと個性の関係を整理すると、こうなる。
AIの強み
- 情報の整理
- 論理構成
- 大量生成
- テンプレ化
AIの弱み
- 独自の感情表現
- 体験談のリアリティ
- 書き手の価値観のにじみ出し
AIは“心の温度”を測れない。
論理の整合性は保てても、読者の胸をざわつかせる体験談は生み出せない。
それはまるで、無機質なナビゲーション音声のように正確だが、魂のない文章だ。
人が覚えているのは「事実」ではなく「物語」。
物語は、書き手の視点や感情がなければ成立しない。
マーケティング調査(2024年)でも、AI生成文章より「体験談+教訓」の記事の方が
平均滞在時間は2倍以上長いと報告されている。
読者は正確な情報よりも、「そこで誰かが感じた生の揺れ」を求めているのだ。
「副業者に残された武器」
僕が学んだのは、AIに勝とうとするのではなく、AIが持てないものを前面に出す戦略だ。
- 僕しか経験していない失敗談を掘り下げる
- 感情の揺れや葛藤を隠さず書く
- 成功よりも過程や迷いを丁寧に描く
副業をする人間にとって効率化は大事だ。
借金を抱えていればなおさら「時間当たりの成果」を求めてしまう。
けれど効率化の果てに残ったのは“無風のアクセス”だった。
逆に、泥臭い失敗や恥ずかしい体験を赤裸々に書いた記事だけは、
自分でも「これは残せる」と思えた。
「借金返済のために効率化を求めた僕が、最後に残したのは“感情の凸凹”だった」
これは皮肉だが、紛れもない現実だった。
つまり僕のような副業者に残された武器は、“感情の凸凹”と“過程の物語”なのだ。
「不完全さは武器になる」
“自分の個性”はAIに勝てるのか?
答えは「正面からは勝てないが、土俵を変えれば勝てる」だ。
AIは速く、正確で、整っている。
でも人間は遅く、偏っていて、感情的だ。
その不完全さこそが、読者の心を動かす。
僕はこれからも、AIの力を借りながら、あえて泥臭い文章を書き続ける。
完璧な情報はAIに任せる。
だが、借金返済に苦しみ、挫折し、笑い飛ばすような感情の揺れは僕にしか書けない。
副業時代の“個性”の生かし方はここにある。
効率の裏に感情を添えること。
そうすれば、AIと人間の共存の中でも、自分の言葉は確かに届く。

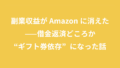
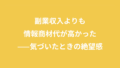
コメント